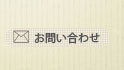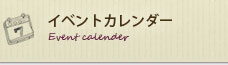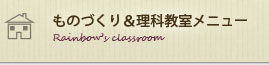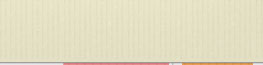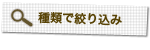磁力線の特性を理解しよう2020-06-24 02:34 磁力線の特性を理解しよう2020-06-24 02:34 |
|---|
| 【ねらい】 電気とは何か,磁力線とは何かを理解するために,磁力線を発生する磁石や電磁石について色々な実験を行い,磁力線のはたらきを理解させる 【対象】 小学5年生 【実施内容】 宙に浮く磁石の実験装置を作成する フェライト磁石1個を計量する もう1個の磁極を考慮して重ねて計量する 電流と磁力線の働きについて実験を行う 地球も大きな磁石であることを確認・納得させる 【主催】 公益社団法人 日本技術士会 中部本部  :download :download
|
 モーターのはたらきと簡易モーターの製作2020-06-24 02:02 モーターのはたらきと簡易モーターの製作2020-06-24 02:02 |
|---|
| 【ねらい】 電気とは何かを理解させ,電流と磁力線の関係を理解させるために,磁力線の応用実験を行い,電流が流れると磁針(方位計)が触れることを確認させる 【対象】 小学5年生 【実施内容】 電流と磁力線のはたらきについての実験を行う 磁針(方位計)近くの電線に電流を流し磁針の振れることを確認する 銅線とフェライト磁石を使ってモーター(簡易型)を作る モーターに電気を流し,モーターの回転を確認する 私たちの生活の場から電気が無くなったらどうなるかを考えさせる 【主催】 公益社団法人 日本技術士会 中部本部  :download :download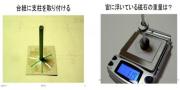
|
 シャボン玉講座2011-02-15 16:47 シャボン玉講座2011-02-15 16:47 |
|---|
| 【ねらい】 シャボン玉を通じて、分子の機能や性質を体験する。また、洗剤として毎日利用している界面活性剤を理解する。表面張力で縮もうとする膜と、閉じ込められた気体が作る形を楽しみ、なぜそうなるのか考える。 また、どんな形が作れるかを工夫する。高学年では、膜の形状と数学で登場する関数との関係も連想してみる。 【内容】 1.小さなシャボン玉をまず見せる 2.大きなシャボン玉を映像で見せる 3.水の膜(壁)がどうして出来るか説明 4.物質としてのシャボン玉:石けんと界面活性剤の歴史・環境問題について解説 5.生物とシャボン玉の関係:生物の細胞膜との関わりを説明 6.シャボン玉膜の力学:ゴム膜のような張力膜であることを説明 7.シャボン玉建築の魅力について説明 8.大きなシャボン玉、小さなシャボン玉、シャボン玉建築を実演 9.十分時間に余裕があれば、各自工夫して新しいシャボン玉建築を作る 【対象】 小学1年生~中学3年生 【主催】 静岡大学工学部化学バイオ工学科 戸田三津夫准教授 |