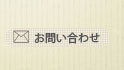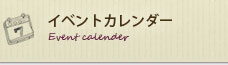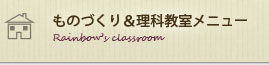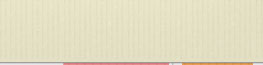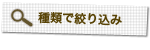紙飛行機教室2024-05-29 02:40 紙飛行機教室2024-05-29 02:40 |
|---|
| 【ねらい】 紙飛行機の製作と飛ばすための調整を通じて、作り試す楽しさへの気づきや、空気の流れとその作用への興味のきっかけとなることを期待します。 【対象】 小学3年生~ 【実施内容】 要件により、折り紙機、ホチキス機、スチレン機などから題材を選択します。 当日は、簡単な説明、製作の後、実際に飛ばします。飛び方の変化を観察しながら調整していくことで、よく飛ぶ飛行機になります。 【主催】 楽しい紙ヒコーキひろば浜松  :download :download


|
 レモンの成分で実験しよう2024-05-29 02:37 レモンの成分で実験しよう2024-05-29 02:37 |
|---|
| 【ねらい】 レモン味のジュース、あめ、ドレッシングとレモンは食卓の人気者です。そんなレモンの成分を使った実験です。この実験で、レモンの成分の働きを理解し、なぜこうなるのかを考えながら実験することで、日常の中での科学的な気づきを促進し、科学的思考が養います。 【対象】 小学4年生~中学2年生 【実施内容】 ①ビタミンCの還元作用 ヨウ素液を透明にします。(サイエンスマジック風に行います。) ②クエン酸のキレート作用 古い10円をぴかぴかにします。 ③リモネンがゴムや発泡スチロールを溶かす 発泡スチロールに手形をつくります。 など 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 SDGs 環境問題と私たちの暮らし・未来2024-05-29 02:22 SDGs 環境問題と私たちの暮らし・未来2024-05-29 02:22 |
|---|
| 【ねらい】 環境問題が私たちの暮らしや未来にどのような影響を及ぼしているかを理解し、私たち一人ひとりが、環境問題の解決に取り組むことができることを、パワーポイントを使って理解します。 授業の最後には、自分たちができることを発表する機会を設け、行動を起こす意欲を高めます。 【対象】 中学生 【実施内容】 ①いろいろな環境問題 ②地球温暖化 Yes No ③持続可能な社会を目指して ④水素を使った実験 生徒全員でホースを手に持ってもらいます。ホースの中で水素を燃やしますと、 ホースの中を炎が走ります。ホースは温かくなり、生成した水によって曇ります。 ⑤自分として取り組んでいきたい目標や課題(グループワーク・発表) など 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 生物の相互作用と進化2024-05-29 02:19 生物の相互作用と進化2024-05-29 02:19 |
|---|
| 【ねらい】 地球上の生物が互いに関係を持ちながら生活していることを理解し、単なる弱肉強食だけでなく、さまざまな関係が存在します。生物間の相互作用と進化について、例を挙げながらパワーポイントで説明します。また、高校模擬授業としても応用が可能です。 【対象】 中学生 【実施内容】 ①捕食者被食者の関係 ②共生と寄生 ③食物連鎖 ④東大の入試問題に挑戦 ⑤水中シャボン玉から進化を考える(実験・グループワーク) など 下の写真はミドリガイ 動物でありながら葉緑体で光合成を行うことができます。これは、ミドリガイの祖先が植物から取り込んだ葉緑体を制御する遺伝子を持っているためです。このような遺伝子の柔軟性は、生物の進化に大きな影響をもたらしています。 クイズを多く取り入れた内容です。 講義30分、実験20分です。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 ボトルウェーブの科学2024-05-29 02:17 ボトルウェーブの科学2024-05-29 02:17 |
|---|
| 【ねらい】 水と油のそれぞれの性質の違いを利用した実験です。ボトルウェーブにエネルギーはどのように伝わるのか?なぜこの現象や反応か起こるのか?など、考えながら進めます。 【対象】 小学生~中学生 【実施内容】 ①ボトルウェーブにエネルギーはどう伝わったか? ②ボトルウェーブの中を進む水滴? ③ボトルウェーブの中で化学反応?(色が変化します) など、最後に各自がつくったボトルウェーブの中に、水と油の境に浮かぶビーズを入れ て、お土産になります。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 中が知りたくなる科学2024-05-29 02:15 中が知りたくなる科学2024-05-29 02:15 |
|---|
| 【ねらい】 『なぜ?どうして!』ちょっと不思議な現象を科学で解明します。この科学工作を通じて、科学的な思考力を養い、科学への興味・関心を高めることができます。 【対象】 小学生 【実施内容】 ①浮かぶ3D映像(立体映像をつくります) ②見える見えない不思議な箱(ハーフミラーを使った立方体です) または、お金が消える貯金箱(鏡を使った立方体です) ③水を入れると文字が読める(水の屈折実験です) など、対象学年によって、薬品を使った科学マジックも可能です。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 温度で色が変わる液晶しおりをつくろう2024-05-29 02:13 温度で色が変わる液晶しおりをつくろう2024-05-29 02:13 |
|---|
| 【ねらい】 植物繊維からつくられる温度で色が変わるコレステリック液晶(食品添加物)を使ってしおりをつくります。色が変化する現象には、目には見えない分子構造の変化があることを理解します。 【対象】 小学生~中学生 【実施内容】 ①化学繊維を抽出します。 ②動物繊維を観察します。 ③植物繊維を取り出します。 ④温度で色が変わる液晶しおりをつくります。 など、途中でクイズを入れながら楽しく実験します。お土産となる液晶しおりはとても きれいです。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 科学の力で回転グッズをつくろう2024-05-29 02:11 科学の力で回転グッズをつくろう2024-05-29 02:11 |
|---|
| 【ねらい】 物体が動くときには必ず力が働いています。回転をテーマに、どのような力がどの方向からそして、どのように伝わっているのかを考えながら進めていきます。 【対象】 小学生~中学生 【実施内容】 ①回すと広がるちょうちんごま(小学生対象) ビュンビュンごまが横向きに回転するグッズとすると、縦向きに回転するグッズです。 ②まゆ玉コロコロ(小学生対象) カイコのまゆを使った江戸時代からある回転グッズです。 ③ぶら下がり釘の回転グッズ(小中学生対象) 磁力と摩擦が関係した回転するグッズです。 ④回転どっちが早い?(中学生対象) エネルギーの変換がポイントです。 ⑤ぶら下がり回転モーター(中学生対象) フレミングの左手の法則を使った単極モーターをつくります。 など 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 光の科学“光の宝石箱をつくろう2024-05-29 02:08 光の科学“光の宝石箱をつくろう2024-05-29 02:08 |
|---|
| 【ねらい】 日光、照明、ディスプレイなど、光は私たちの生活に欠かせません。この光には、波長によって色が分かれたり、反射したり、色を混ぜると違う色になったりと、さまざまな性質があります。それらの性質を、実験によって確かめます。 美しい実験が多いので、科学への興味・関心を高めることができます。 【対象】 小学生 【実施内容】 ①コップの中に虹をつくろう(コップを2つ合わせて、穴からのぞくと中に虹が見えま す。) ②光の宝石箱(カップを回転させることで、カップの中を通る光の色が変化して、いろ いろな色が次々と現れます。) ③水を入れると見えるコップ(光の屈折を利用した工作です。) など、途中で虹クイズを入れることで考える力も育みます。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 結晶の観察ができる結晶コースターをつくろう2024-05-29 02:05 結晶の観察ができる結晶コースターをつくろう2024-05-29 02:05 |
|---|
| 【ねらい】 結晶とは、同じ形をした小さな粒が規則正しく並んでできたものです。目の前で結晶が成長する様子を観察します。 美しい結晶の成長過程を観察することで、原子や分子の規則性を間接的に知ることができます。 【対象】 小学生 【実施内容】 ①尿素クイズ(どこでつくられるの、においはするの、溶かすと 温度がどう変わる度など、実際に尿素を使って説明) ②結晶コースター作り(針状結晶が成長する様子を観察) ③まるで雪みたい(試験管の中で結晶が次々と現れます) など 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 磁石の力でつくる“アニマル回転グッズ2024-05-29 01:58 磁石の力でつくる“アニマル回転グッズ2024-05-29 01:58 |
|---|
| 【ねらい】 磁石にはN極とS極があり引き合ったり、反発したりする性質があります。また、目には見えなくても磁力線が働いています。この実験で、磁石の基本的な働きを理解し、磁石が物体に及ぼす影響を体験することで、科学への興味・関心を高めることができます。 【対象】 小学生 【実施内容】 ①手に刺さるモール(目で見ることができない磁力線を見ることができます。) ②キツツキのドラミング(N極とS極を使った工作です。) ③アニマル回転グッズ(磁石が反発する性質を利用し、回転するグッズをつくります。) 磁石が反発する性質を利用し、回転するグッズをつくります。 など、途中で磁石クイズを入れることで考える力も育みます。 【主催】 科学実験チャレンジ塾  :download :download
|
 水溶液の性質を利用して水をきれいにしよう2020-06-24 02:41 水溶液の性質を利用して水をきれいにしよう2020-06-24 02:41 |
|---|
| 【ねらい】 ①6年生理科の単元“水溶液の性質”の発展学習である。まず水溶液の変化の面白さを体 感させる。 ②その水溶液の性質が水をきれいにする技術に使われていることと、それによって快適な 水環境が維持されていることを伝える。 ③環境学習へ発展させ、川や海をきれいにするために私たちにできることは何かを考える。 【対象】 小学生 【実施内容】 コーヒー、ウーロン茶、牛乳の3種類の液を各班へ配り、下記の①②の実験を行う。それぞれの液が、どのように変化してきれいな水になるかを観察する。 ①液をビーカーに100mLずつ取り、次亜塩素酸ナトリウム液を5mLずつ注入し、ガラス棒で 撹拌する。そのまま静置し、変化の様子を見る。 ②液100mLに酢を2mLずつ加え、ガラス棒で軽く撹拌した後、ろ紙でろ過する。ろ過後の液 の変化の様子を見る。 【主催】 公益社団法人日本技術士会中部本部理科支援小委員会  :download :download
|
 振り子の特性を理解しよう(改)2020-06-24 02:38 振り子の特性を理解しよう(改)2020-06-24 02:38 |
|---|
| 【ねらい】 遊園地などにあるブランコの振れや,振り子時計,メトロノームなどの振れる運動について,(振り子の)長さ,振れ幅,周期,錘の重さ等の関係を測定して,振り子の特性を理解する 【対象】 小学5年生 【実施内容】 自分で振り子を作り,振り子を振らせてみる 錘の重さや振れ幅を変えて,振り子を振らせてみる 振り子の長さを変えて,同じように振らせてみる 振り子の長さ,振れ幅,錘の重さを変えて,振り子の周期を計る 前項の測定結果について,それぞれの関係を観察する 【主催】 公益社団法人 日本技術士会 中部本部  :download :download
|
 磁力線の特性を理解しよう2020-06-24 02:34 磁力線の特性を理解しよう2020-06-24 02:34 |
|---|
| 【ねらい】 電気とは何か,磁力線とは何かを理解するために,磁力線を発生する磁石や電磁石について色々な実験を行い,磁力線のはたらきを理解させる 【対象】 小学5年生 【実施内容】 宙に浮く磁石の実験装置を作成する フェライト磁石1個を計量する もう1個の磁極を考慮して重ねて計量する 電流と磁力線の働きについて実験を行う 地球も大きな磁石であることを確認・納得させる 【主催】 公益社団法人 日本技術士会 中部本部  :download :download
|
 モーターのはたらきと簡易モーターの製作2020-06-24 02:02 モーターのはたらきと簡易モーターの製作2020-06-24 02:02 |
|---|
| 【ねらい】 電気とは何かを理解させ,電流と磁力線の関係を理解させるために,磁力線の応用実験を行い,電流が流れると磁針(方位計)が触れることを確認させる 【対象】 小学5年生 【実施内容】 電流と磁力線のはたらきについての実験を行う 磁針(方位計)近くの電線に電流を流し磁針の振れることを確認する 銅線とフェライト磁石を使ってモーター(簡易型)を作る モーターに電気を流し,モーターの回転を確認する 私たちの生活の場から電気が無くなったらどうなるかを考えさせる 【主催】 公益社団法人 日本技術士会 中部本部  :download :download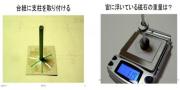
|
 私たちのくらしと防災 ー大津波と液状化ー2020-06-24 01:53 私たちのくらしと防災 ー大津波と液状化ー2020-06-24 01:53 |
|---|
| 【ねらい】 1.日本ではなぜ地震が多いかを学習する 2.地震や津波のおきるしくみ、液状化現象のしくみを学習する 3.防災対策の重要性や防災情報を理解し、毎日のくらしの中に役立てて行く 【対象】 小学生 【実施内容】 ■最近日本各地で良くおきる大きな自然災害について説明します ■地球の表面をおおうプレートの動き、地震、津波がおきるしくみを絵図を用いて説明します ■南海トラフ巨大地震と防災対策について説明します ■ビーカー、砂、サイコロなどを用いて、地震時の液状化現象を全員が体感します ■昨年から実施されている5段階の避難情報について説明します ■実施内容、時限数は相談に応じます 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会  :download :download
|
 「暗くなったら自動で点灯する」仕組みをプログラミングしよう2020-06-24 01:44 「暗くなったら自動で点灯する」仕組みをプログラミングしよう2020-06-24 01:44 |
|---|
| 【ねらい】 身の回りには電気の性質や働きを利用した道具があること等をプログラミングを通して学習する。日中に光電池でコンデンサに蓄えた電気を夜間の照明に活用する際に、どのような条件で点灯させれば電気を効率よく使えるかといった問題について、児童の考えを検証するための装置と通電を制御するプログラムとを作成し実験する。 【対象】 小学生 【実施内容】 ・周囲の明るさ(照度)を検知する光センサーの回路図を説明する。 ・通電を制御するスイッチをつないだ、発光ダイオード(LED)の点灯回路図を説明する。 ・光センサーとLEDを内蔵したmicro:bitを制御するプログラムの作成に取り組みます。 ・電気を無駄なく効率よく使うためには、どの条件をどのように設定すればよいかなど実験する。 【主催】 公益社団法人日本技術士会中部本部理科支援委員会 静岡県グループ  :download :download
|
 水中に住む小さな生き物を観察しよう2020-06-24 00:56 水中に住む小さな生き物を観察しよう2020-06-24 00:56 |
|---|
| 【ねらい】 ①顕微鏡を覗いて、いろいろな小さな生き物を観察することの楽しさを体感し、水中には多くの種類の小さな生き物が存在することを伝える。 ②その中には、水をきれいにする働きのある小さな生き物も居れば、たくさん増え過ぎると困る(赤潮など)小さな生き物も居ることも伝える。 ③さらに、川や海を汚さないようにするために私たちにできることは何かを考える。 【対象】 小学生 【実施内容】 ①微生物動画の紹介:10分 ②観察実施内容と注意事項の説明:10分 ③自由観察及びスケッチ:50分(10分の休憩を含む) ④講師からの解説及び質疑応答:15分 ⑤後片付け:5分 【主催】 公益社団法人日本技術士会中部本部理科支援小委員会  :download :download
|
 月の満ち欠け、月食・日食はなぜ生じるか2020-05-28 05:36 月の満ち欠け、月食・日食はなぜ生じるか2020-05-28 05:36 |
|---|
| 【ねらい】 地球から見た月は一か月の間で、満月、半月、三日月、新月と形は変わっていくが、月そのものが姿を変えるわけではない。又月食や日食で、月や太陽が一時的に見えなくなる。 天体のみならず自然現象を「なぜだろう?」という疑問を持って観察することの面白さや大切さを、実験で体験する。 【対象】 小学生 【実施内容】 ■実験①:講師は月にみたてた黄色ボールにライトを当て、児童はそれぞれの場所で、黄色ボールのライトで光る部分をスケッチし、ボールが見る場所により異なる形となることを認識させる。自ら光る太陽と異なり、月は太陽光の反射が三日月や満月などの姿として見えることを講師は説明する。 ■実験②:机上に置いた地球にみたてた小ボールの位置を中心にして、月にみたてた黄色ボールを45度づつ位置を移動し、一方向から太陽光にみたてたライトを当て、地球位置から見た黄色ボールの光る部分(満月、半月、三日月、新月を模した形)を児童はスケッチする。 ■実験③:講師は日食、月食における太陽、地球、月の位置関係を実験で示し、現象を実験で説明する。 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会 静岡県グループ  :download :download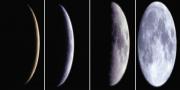
|
 バイオトイレを知ろう2020-05-28 05:06 バイオトイレを知ろう2020-05-28 05:06 |
|---|
| 【ねらい】 ひとは食べては排泄する。この排泄物を炭酸ガスと水に分解するトイレを説明する。 そのトイレは、環境バイオトイレと言って、富士山頂に設置した。 し尿の垂れ流しを無くし、トイレ問題が悩みの種であった富士山の環境改善に貢献した。 バイオトイレの原理は、バイオ(微生物)が主役である。微生物が排泄物を食べてトイレの機能を果たすしくみを理解する。 【対象】 小学生 【実施内容】 ■環境バイオトイレ「自己完結型・循環式水洗トイレ」の機能を手順に従い説明する。 ■バイオが働く環境を微生物の食物連鎖を例に説明する。 ■富士山頂バイオトイレの設置経験事例を話しする。 ・どうして山頂に運ぶ? ・高山病は怖い。 ・3S(SPEED、SAFETY、STEADY:早く、安全に、着実に)の意味を説明する。 ■トイレは災害時にも必要。日頃の備え、心構えなどにも触れ、トイレ環境を考える。 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会 静岡県グループ  :download :download
|