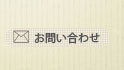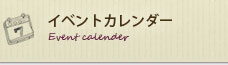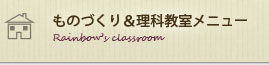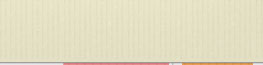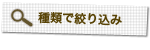竿ばかりをつくろう2012-10-26 11:11 竿ばかりをつくろう2012-10-26 11:11 |
|---|
| 【ねらい】 つり合いを利用した竿ばかりを自作して、いろいろなものの重さを測ることにより、この規則性を体感する。 【対象】 小学6年生 【実施内容】 ■つり合いを利用した竿ばかりを自作して、いろいろなものの重さを測ることにより、この規則性を体感する。 【主催】 浜松理科教育研究会 |
 ろうそく作りに挑戦しよう2012-10-24 15:55 ろうそく作りに挑戦しよう2012-10-24 15:55 |
|---|
| 【ねらい】 ナンキンハゼの実から木の実ろうそくをつくり、木の実ろうそく、和ろうそく、洋ろうそくなどの燃える様子を観察する。 【対象】 小学6年生 【実施内容】 ■ナンキンハゼの実をコーヒーミルで砕く(5分) ■なべに砕いた実と水、重曹を入れて煮る(15分) ■煮立ったところでクエン酸で中和し、なべを冷やしてろう分を集める(15分) ■ナンキンハゼのろうそく、和ろうそく、蜜ろうそく、洋ろうそくの燃え方を観察する(10分) 【主催】 浜松理科教育研究会 |
 虫の家をつくろう2012-10-24 15:46 虫の家をつくろう2012-10-24 15:46 |
|---|
| 【ねらい】 身近な昆虫を観察する。昆虫には卵、幼虫、さなぎ、成虫と変態する種類とさなぎを作らない不完全変態する種類があることを、チョウとコオロギを飼育することにより知る。 【対象】 小学3年生 【実施内容】 ■チョウとコオロギの飼育の仕方を聞く(5分) ■コオロギ採集容器づくり(10分) ■コオロギとチョウの飼育容器づくり(15分) ■できた飼育容器にチョウとコオロギ、エサを入れる(10分) ■昆虫の変態の仕方を発表する(5分) 【主催】 浜松理科教育研究会 |
 笛をつくろう2012-10-24 15:39 笛をつくろう2012-10-24 15:39 |
|---|
| 【ねらい】 音は物体の振動によって生じ、その振動が空気中などを伝わること。音の大小や高低は、発音体の振幅と振動数に関係することを笛を自作して確かめる。 【対象】 中学1年生 【実施内容】 ■音の大小や高低は発音体の振動の振幅と振動数に関係すると説明を受ける(5分) ■ブタ笛を組み立てて鳴らす(5分) ■ブタ笛に長さの違うゴムホースをつけて鳴らし、音の高低を確かめる(20分) ■ストロー笛、おぎ、セミしぐれなどを作り鳴らしてみる(20分) 【主催】 浜松理科教育研究会 |
 ハート型モーターを作ろう2012-10-22 16:03 ハート型モーターを作ろう2012-10-22 16:03 |
|---|
| 【ねらい】 磁石・乾電池・銅線だけで簡単に作ることの出来るハート型モーター。電流と磁場、磁場中で発生する力について学ぶ。 【対象】 中学1年生~3年生 【内容】 ■ハート形モーターの制作 銅線をハート形に曲げ、これと乾電池(軸となる)、強力磁石を組み合わせ、モーターを制作する。 ■モーターの回転の観察 磁石の向きを変えたり、銅線の形状を変えたりしながら、モーターの回転を観察し、銅線に働く力について考える。 ■磁場の測定(発展課題) 【主催】 静岡大学工学部 共通講座物理教室(浜松RAIN房) 
|
 洗剤で泡だらけ。ゴシゴシ擦って傷だらけ。これが、環境汚染の原因だ!2012-10-22 15:52 洗剤で泡だらけ。ゴシゴシ擦って傷だらけ。これが、環境汚染の原因だ!2012-10-22 15:52 |
|---|
| 【ねらい】 家庭から出る生活排水が、環境汚染の大きな原因です。家の中の汚れは、大きく分けて2種類。酸性とアルカリ性の汚れです。この原理原則にあった洗剤を効果的に使うこと。この簡単な原則を理解すれば、洗剤の使い方が変わる。子どもたちが理解すれば、日本の環境も大きく変わる! 【対象】 小学6年生~中学3年生 【実施内容】 ■講話「洗剤の起源、特徴」(10分) ■ワーク「知っている洗剤の使用法」(10分) ■市販の洗剤で実習(10分) ■講話「汚れの原理原則」症例をもとに解説(20分) 【主催】 (有)メイ・グロー http://loiseau-blanc.com/ 
|
 ロボットを動かして、ロボットのしくみを知ろう2011-12-09 15:31 ロボットを動かして、ロボットのしくみを知ろう2011-12-09 15:31 |
|---|
| 【ねらい】 自分でプログラムを組んでロボットを動かすこを通じて、「ロボットとは何か(ロボットの制御・センサーの役割等ロボットのしくみ)」について体得する。中学生向けプログラムでは、ロボットの制御に用いられる簡単なデジタル回路についても学ぶ。 【内容】 ■身のまわりにあるロボットの紹介とロボットの基本的なしくみのお話し ■ノートPCを用いた実習用ロボットの動かし方・プログラミングの練習 ■ロボット制御プログラミングの実践(課題+自由プログラム)プログラミング技法の紹介 ※中学生向け ■デジタル回路の説明と制御回路の制作 【対象】 小学5年生~中学2年生 【主催】 静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsozo/  :download :download |
 浜名湖の生物を知ろう2011-12-09 13:47 浜名湖の生物を知ろう2011-12-09 13:47 |
|---|
| 【ねらい】 浜名湖及び遠州灘に生息する、魚介類の種類や生態について知る。また、これら魚介類とともに生きていく我々環境・生態系や身近な水産業についても考える。 【内容】 ■上映プログラム「養殖と栽培漁業について」(他3プログラム内から選択)上映 ■講話「浜名湖の生物と環境について」 ■館内ガイド解説後自由見学 【対象】 小学1年生~中学3年生 【主催】 浜名湖体験学習施設ウォット http://www.orange.ne.jp/~ulotto/ |
 「音」の正体をみつけよう~「音楽の街」浜松を楽しもう~2011-12-08 15:49 「音」の正体をみつけよう~「音楽の街」浜松を楽しもう~2011-12-08 15:49 |
|---|
| 【ねらい】 基本的な物理量である「音」の本質を理解させると共に、「音」の出る簡単な道具を児童全員に作成させることにより、「音」に対する興味を持たせる。 【内容】 前半:実験 ■音が聞こえるしくみ 大型スピーカーから発する色々な音に対し、スピーカーのコーン紙を手で触れるなどして、音は空気の振動であることを理解させる。次に、音楽を入力した加振器に、歯でかんだり割り箸の先端を接触させ、骨電導のしくみを理解させる。 ■音の違いの正体 音の波形をプロジェクタに投影しながら、波形を変化させ、音と波形との対応を理解させる正弦波、三角波、方形波、色々な楽器の音、児童の声などを試す。次に、児童の声の波形をフーリエ変換し声の成分となっている正弦波を一つずつ加算してゆき、元の声が合成できるデモンストレーションをする。 後半:ものづくり ■エコーマシンの作成 児童全員に紙コップ2個、バネ1個を配布し、エコーマシンを作る ■ストローラッパの作成 児童全員にストロー1本、厚めのB4色紙を配布し、ストローラッパを作り、合奏する 【対象】 小学5年生~6年生 【主催】 静岡大学工学部 化学バイオ工学科  :download :download |
 学校プールヤゴ救出作戦2011-12-08 14:48 学校プールヤゴ救出作戦2011-12-08 14:48 |
|---|
| 【ねらい】 学校プールの清掃時に、プール内で育ったヤゴを救出することで、自然への興味・関心を高める。また、救出したヤゴを育て羽化させることで自然の不思議さに触れさせ、生命尊重の気持ちも育てる。 【内容】 学校プール清掃時、水位を足のくるぶしくらいまで下げておく。 ■タモでプールのヤゴを捕獲する ■バットにトンボの種類別に入れる。 ①アカトンボ型 ②シオカラトンボ型 ③イトトンボ型 ■集計をして、アカトンボ型の割合を計算する ■各自ビンのわりばしを立てたヤゴ飼育容器を準備し、ヤゴを1匹いれる。エサをやり飼育する ■どんなトンボがかえったか記録する 【対象】 小学1年生~中学3年生 【主催】 NPO法人 桶ヶ谷沼を考える会 |
 佐鳴湖を知ろう2011-12-08 11:46 佐鳴湖を知ろう2011-12-08 11:46 |
|---|
| 【ねらい】 身近な「佐鳴湖」の環境を考えることで、浜松の水、人間と環境、湖の生態系などについての理解を深め、毎日の暮らしや未来の社会について考えてみる。 【内容】 1.浜松の佐鳴湖がほかの地域の湖に比べてひどく汚れたのはなぜか 2.人が生きていくと、環境はどのような影響を受けるか 3.浜松地方の水の流れ、利用と移動 4.佐鳴湖はどう汚いか 5.きれいになりつつある佐鳴湖 6.佐鳴湖の汚さ、きれいさをはかってみよう 7.佐鳴湖は本当に汚いか 【対象】 小学1年生~中学3年生 【主催】 静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクト http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsanaruk/ (※このプロジェクトでは、これまで佐鳴湖の汚染原因の解明と浄化対策の研究を行ってきました。この講座では、プロジェクトの活動や県、市、市民の活動なども関連させて実施したいと思います)  :download :download |
 ほんとうに逆立ちする逆立ちコマ2011-02-15 16:50 ほんとうに逆立ちする逆立ちコマ2011-02-15 16:50 |
|---|
| 【ねらい】 逆立ちゴマを色々な条件で作成し、コマがどのように回転するのかを観察する。重心、回転の性質、摩擦力など、力学の基本的な概念を観察する。 【内容】 一見普通に回っているが、不思議と逆立ちしていくコマを制作する。 樹脂製のコマを組立て、やすりを使って表面を整え、逆立ちするまで試運転し、2人一組で色付けして完成。 なぜ逆立ちするのか?逆立ちする仕組みについて学習する。 【対象】 小学生~一般 【主催】 静岡大学工学部 共通講座物理教室(浜松RAIN房) 【教材/テキスト】※ダウンロードしてお使いください。  :download :download

|
 シャボン玉講座2011-02-15 16:47 シャボン玉講座2011-02-15 16:47 |
|---|
| 【ねらい】 シャボン玉を通じて、分子の機能や性質を体験する。また、洗剤として毎日利用している界面活性剤を理解する。表面張力で縮もうとする膜と、閉じ込められた気体が作る形を楽しみ、なぜそうなるのか考える。 また、どんな形が作れるかを工夫する。高学年では、膜の形状と数学で登場する関数との関係も連想してみる。 【内容】 1.小さなシャボン玉をまず見せる 2.大きなシャボン玉を映像で見せる 3.水の膜(壁)がどうして出来るか説明 4.物質としてのシャボン玉:石けんと界面活性剤の歴史・環境問題について解説 5.生物とシャボン玉の関係:生物の細胞膜との関わりを説明 6.シャボン玉膜の力学:ゴム膜のような張力膜であることを説明 7.シャボン玉建築の魅力について説明 8.大きなシャボン玉、小さなシャボン玉、シャボン玉建築を実演 9.十分時間に余裕があれば、各自工夫して新しいシャボン玉建築を作る 【対象】 小学1年生~中学3年生 【主催】 静岡大学工学部化学バイオ工学科 戸田三津夫准教授 |
 木片ヨットを作ろう!2011-02-15 16:33 木片ヨットを作ろう!2011-02-15 16:33 |
|---|
| 【ねらい】 天竜の杉を使い、帆を持ったヨットを作成し、風上に向かって走らせる。小さいヨットで追い風が一番遅いことや風上に向かって走る原理を学ぶ。風による揚力や力の方向(ベクトル)の概念をわかりやすく体得する。 【内容】 ~なぜヨットは風上にむけて走るか~ 木片のヨットを使ってヨットが走る仕組みについて学習する。実際に天竜杉とペーパーホルダーでヨットを作り、色づけして自分だけのオリジナルヨットの完成させ、実際に走らせてみる。帆(セール)などの形や位置でヨットの性能が変化するところにおもしろさがある。 小学生~中学生まで年齢にあった講習内容にすることができる。 【対象】 小学3年生~中学3年生 【主催】 浜名湖海の駅連絡協議会事務局 
|